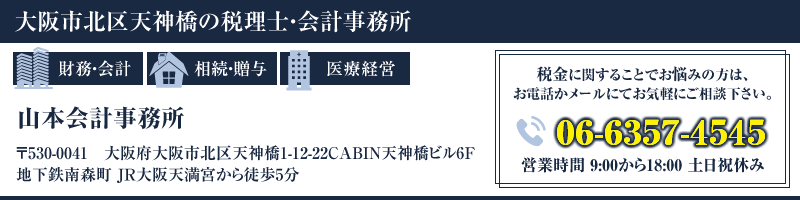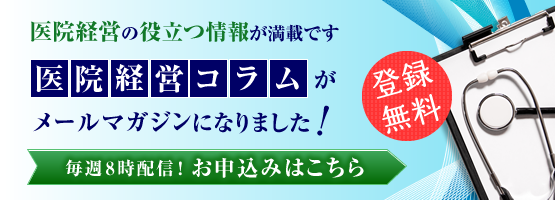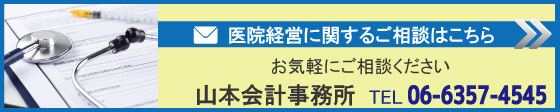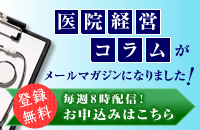前回は「医療機器の導入に必要となる開業資金について」お話しましたが、
今回は「資金調達に必要となる金融の基礎知識」について
お話させていただきたいと思います。
開業にあたっては、さまざまな資金が必要となります。
開業するための土地や建物、医療機器などの設備資金のほか、
人件費や薬剤費、リース料、開業後の先生ご自身の生活費などの
運転資金も考えて、資金調達を行わなければなりません。
ここでは資金調達するための金融の基礎知識を見ていきましょう。
ポイント1
資金調達の方法には「公的融資」と「民間融資」とがあります。
公的融資とは、政府系金融機関や信用保証協会の信用保証付き融資など
開業時に利用しやすくなっている制度です。
保証機関を利用する場合がほとんどで保証料が必要となります。
民間融資とは、民間金融機関からの融資で、
開業医向けローンの商品を用意している金融機関もあります。
連帯保証人を求められる場合が多くあります。
ポイント2
返済期間の設定には注意が必要です。
返済期間の設定が長いと金利が高くなり、
したがって支払利息総額も高くなります。
開業当初は患者数もそれほど多くはなく、
また保険診療の入金も2ヶ月間のタイムラグがあるため、
資金繰りが上手くいかないなんてことのないように
しっかりと計画し返済期間を適切に設定してください。
ポイント3
返済方法には「元金均等返済」と「元利均等返済」があります。
「元金均等返済」とは、借入元金の返済金額を毎月均等にし、
プラス利息分を返済するものです。
「元利均等返済」とは、借入元金と利息の合計を
毎月均等に返済するものです。
支払利息総額の少ない「元金均等返済」を利用するのが一般的ですが、
これだと当初の返済額が大きくなるため、
「据置期間」というものが設けられており、
一定期間だけ元金の返済をせずに利息のみを支払うことができます。
金融機関に相談してみるとよいでしょう。
次回は「歯科・クリニック開業前の出資は開業費になるか」について